生活習慣病とは
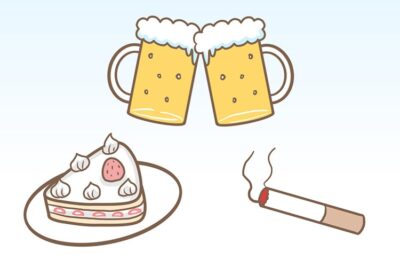
生活習慣病には、高血圧、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)、高尿酸血症(痛風)などがあります。いずれも過食や偏食、運動不足、嗜好品(タバコ・お酒など)の摂取過多などの生活習慣が主な原因となって起こる慢性疾患であり、生活習慣を見直すことによって予防・改善できる余地の大きいのが特徴です。
これまでの生活スタイルを一度に変えること(行動変容)は困難さを伴い、勇気や決断を要しますが、目標を低く定めたり、一定期間限定のお試し期間を設けるなど、永遠に厳密に習慣を変えるのではなく、ちょこっと変える、一旦休憩する、成果を確かめて何が自分に効果的かを知る、など、宝探しの気分で気軽にとりかかり、失敗しても自分を責めすぎないようにする、など時間をかけてやってみましょう。
自覚症状が無くても早めの対策を
生活習慣病は、一つ一つは軽症でも、いくつもの疾患が重なることが少なくありません。そして、疾患が重なることによって相乗的に各症状がひどくなったり、動脈硬化(動脈が硬くなって弾力性を失うこと)を進行させたりして、脳卒中や心筋梗塞などの重大な疾患に結びつき、取り返しのつかない状況にも至りかねません。
そうした深刻な状況を招かないように、たとえ自覚症状が無くても、早めに生活習慣病を改善するための対策を講じましょう。
基本的には、生活習慣病はいずれの病気であっても、やはり生活習慣の改善、特に食事療法ならびに運動療法が治療の中心になります。必要な場合は、薬物療法も併用します。
こんな方に受診をお勧めします
- 健診などで何かしら検査数値の異常を指摘された
- 40歳以上である
- 20歳の頃より体重が10kg以上増えた
- タバコを吸う
- お酒をよく飲む
- 清涼飲料水を常飲している
- 運動習慣が無い
- 車を使うことが多く、あまり歩かない
- ストレスが溜まっている
- 睡眠時間が十分でない
- 食生活に問題がある(下記)
- 朝食を抜く
- 夜遅く食べる
- 間食が多い
- 食事時間が不規則
- 食べるのが早い
- 濃い味付けを好む
- 脂っこい料理を好む
- ファストフードやインスタント食品をよく食べる
- 満腹になるまで食べてしまう
など
代表的な生活習慣病
高血圧

血圧が高い状態が続いている場合に「高血圧症」と診断され、高血圧が続くと血管の壁に強い圧力がかかり血管を傷つけて、血管の壁が硬く狭くなり、心臓では狭心症や心筋梗塞、心肥大、また、脳梗塞、脳出血、腎臓病(腎不全)、大動脈瘤などを引き起こします。
人によっては、病院ではいつも高いけれど、家では低いから高血圧じゃない、という方がおられますが、如何でしょうか。
大事なことは血圧は一定ではなく、1日の中でも変動する点です。
特に、起床時の血圧が高い方は、脳卒中や心筋梗塞を引き起こす可能性が高く、起床時の血圧が高い方は、他の血圧が高く無くても治療を受けていただきたいと思います。
高血圧症の原因は特定されていませんが、多くは原因が明確ではない、「本態性高血圧症(ほんたいせい・・)」と呼ばれるタイプであり、遺伝的な要因と食生活(塩分過多)や嗜好品(タバコ・お酒など)の摂り過ぎ、運動不足や睡眠不足、精神的ストレスなどの生活習慣が影響します。
その他のタイプとしては、他の病気が原因で血圧が高くなる“二次性高血圧症”があります。
特に若い方の高血圧症では、アルドステロンというホルモンが副腎から過剰に分泌され塩分と水が体に溜まることで血圧が上がる「原発性アルドステロン症」という病気があり、アルドステロンは血管を傷つけ易く、早期の診断を要する大事な病気ですので、若年者でも血圧高いと言われたことのある方は検査を受けていただくようお願いいたします。
その他に「睡眠時無呼吸症候群」があります。他の項でも記載しておりますが、就寝中に繰り返し呼吸が止まり低酸素血症になり深い睡眠がとれず、寝ているのに緊張状態の浅い眠りに留まり緊張状態にあるため血圧が高くなりやすく、非常に危険な病気ですので早期に検査を受けて頂きたくお願いします。
また、高血圧と診断されたら「一生薬を飲まないといけないのでは?」、「一度薬を飲み始めたら、一生やめられないのでは?」、と心配される方は多いです。
実際には、生活習慣を見直して、睡眠を整える、塩分制限や運動・強度を変えた運動、筋力アップ、などによりやめられる方もおられます。
血圧の薬は「一生飲まなければいけない重荷」ではなく、血管や臓器を守るための重要なサポーターと考えていただき、上手に飲んでいただければ不安が安心に変わります。
なお、血圧計の購入をお考えの場合には、手くび式血圧計ではなく、上腕式の血圧計の方が信頼できるデータを得やすいとお考えください。特に腕に巻くカフと呼ばれる腕を押さえつける圧迫帯が、腕をかたどったすっぽりと覆うタイプの方が装着しやすく、長く使えると考えます。
糖尿病
糖尿病は、血管内のエネルギー源であるブドウ糖を体の細胞に取り込めず、血液中にブドウ糖(血糖)があふれた状態が続く病気です。
この血糖を細胞に取り込む物質は、「膵臓のβ細胞」が分泌する「インスリン」と呼ばれるホルモンです。
糖尿病の原因は、この①「インスリンの分泌」の低下と、②「インスリンの働き」の低下(「インスリン抵抗性(インスリン働きが邪魔される)」)の2つがあります。
糖尿病の多くの方は、①と②の両方に原因があり、生活習慣(過食や甘いジュースや食べ物の過剰摂取や運動不足)、肥満、ストレスなどが影響する「2型糖尿病」と呼ばれるタイプです。
一方、なにかの原因で免疫機能が異常を起こして自分の膵臓(β細胞)を攻撃する抗体が出るようになり、インスリン分泌が極端に減少して急激に糖尿病が悪化する「1型糖尿病」と呼ばれ、インスリンの補充がすぐに必要な、小児や青年など若くても糖尿病を発症するタイプがあります。
血糖が高い状態が続くと血管壁の細胞(内皮細胞)が傷つけられ、その傷ついたところに炎症細胞が集まりコレステロールなどが沈着して動脈硬化を引き起こし、健常人とくらべて狭心症や心筋梗塞(糖尿病では神経細胞が傷つき、狭心症でも痛みを感じず、突然心筋梗塞を起こす方も少なくありません)、脳卒中、足の血管の閉塞(足の切断)、などを発症する危険度が増加します。
特に高血圧症や脂質異常症(高コレステロール血症)、肥満、喫煙、などの危険因子が重なるとさらに脳心血管合併症を起こし、また、網膜剥離(失明)や腎機能障害、腎不全(尿毒症、人工透析)、等々、これまでの生活(お仕事や日常生活)を諦めないといけなくなり、50歳でも脳梗塞を起こして寝たきりになる方も少なくありません。
治療として食生活の改善は非常に有効です。ただし、目標を高くし過ぎると苦痛になり続けられませんから、期間を設定して達成し易い目標を設定して続けていただきたいと思います。
また、運動は筋肉量の増加につながり、筋肉量の増加は血管内の余分なブドウ糖を筋肉内に取り込み、インスリン抵抗性を改善(インスリンが効きやすくなる)するなど非常に有用ですが、通勤の一部を徒歩にしたり、曜日と時間を決めて運動するなど、長続きできる方法を設定していただき、危険な暑さの夏の期間は大きなショッピングモール内での移動を運動の代行とするなど様々な機会を運動に見立てていただきたいと思います。
食事や運動療法だけでは糖尿病の改善が望めない場合には、疲れ果てた膵臓を守り低血糖を起こしにくい薬剤やインスリン療法を併用することで、早期の改善につながります。
健康診断でHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)の上昇や血糖値の上昇を指摘された場合には「要観察」でも早期に受診をしてください。
HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)とは?;
血糖値は食事の影響ですぐに変動するため、実際には早期の糖尿病であっても絶食で健康診断を受けると“血糖は正常”と判定されるため、早期に糖尿病を発見することができませんでした。
しかし、最近の健康診断ではHbA1cを検査項目に含める健診機関が多くなりました。
その理由は、HbA1cは、当日や前日など短期間の食事の影響を受けない検査のため、早期の糖尿病(隠れ糖尿病)を発見することが可能となり、大変重要な検査項目です。
HbA1cについて説明させていただきます。
赤血球内に含まれる鉄を含むタンパク質であるヘモグロビン(Hb)は肺で酸素を取り込み、全身を巡って体の細胞に酸素を渡す重要な蛋白質です。
この赤血球が全身の血管を巡っているうちにヘモグロビン(Hb)は酸素以外にも血液中のブドウ糖と接触し結合して糖化ヘモグロビンになります(“糖化”=糖に化けた)。
この糖が付いたHb“糖化ヘモグロビン”がすべてのHbのうちのどのくらいの割合かを(%)で表したものがHbA1cです。
赤血球は骨髄で造られて約120日の寿命があるとされ、このためHbA1cは過去1~2ヶ月間の血糖値を反映し、血液検査前日や当日の食事や運動など短期間の血糖値の影響は受けないため隠れ糖尿病(早期の糖尿病)の発見・診断が可能となり、また、治療効果の判定や上記の様々な重要な合併症発症予測にも用いられる重要な検査です。
糖尿病の診断のための基準値としてのHbA1cの値について、糖尿病;6.5%以上、正常は4.6~6.2%、境界型は5.7~6.4%。ただし、健康診断ではより低値でも要精査判定をしている健診機関が多くなっています。
それほど糖尿病は進行させないことが将来の生活、医療費負担、などに直結する重要な病気であるからです。
みなさまには早期のうちに受診をしてください。
特にHbA1cが6.0%以上の方は詳しい検査が必要です。
インスリン療法とは
注射で体外からインスリンを補い、健常な人の血中インスリン変動をできるだけ忠実に再現する治療法です。昨今、良好な血糖コントロールを保って合併症を防ぐために、また膵臓を守るために、糖尿病治療の比較的早い段階からこのインスリン療法を始めるケースが増えています。
脂質異常症(高脂血症)
脂質異常症は、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)が多過ぎる、または少な過ぎる疾患です。
脂質異常症を放置すると動脈硬化が進行し、やがて心筋梗塞や脳卒中などを引き起こす原因となります。脂質異常症は、エネルギー過多な食生活や嗜好品(タバコ・お酒など)の摂り過ぎ、運動不足などの環境的要因が重なって引き起こされると考えられています。
脂質異常症の治療は、生活習慣の改善と薬物療法が基本です。
生活習慣の改善は、血中脂質を下げるだけでなく、動脈硬化の進行防止にも役立ちます。
生活習慣改善の主な内容は、栄養バランスのとれた食生活、適正体重の維持、適度な運動、禁煙などです。なかでも特に重要なのが食事療法です。
高尿酸血症(痛風)
高尿酸血症とは、血液中の尿酸が多くなり過ぎている状態です。尿酸は水分に溶けにくいため、血液中では尿酸塩として存在しています。尿酸が過多になると、針状の尿酸塩の結晶ができ、体のあちこちに溜まって、痛みを引き起こします。これが痛風です。
体の細胞は、毎日の新陳代謝で新しくつくり変えられています。その結果、細胞の核からプリン体という物質が生成されます。このプリン体が、尿酸の元になります。
また、プリン体はレバー類、干し椎茸、魚卵類、えび、かつお、いわしなど一部の魚介類に多く含まれています。そしてアルコール飲料には、尿酸値を上昇させる作用があります。こうした飲食物を好む人は、尿酸値が高くなりやすい傾向があります。
高尿酸血症では、尿酸値を下げることが大切です。それには食事療法として、前記のようなプリン体を多く含む食品の摂取を控えめにし、バランスの良い食事を摂るようにします。禁酒・節酒も心掛けます。特にビールはプリン体を多く含むので注意しましょう。また、食事療法と併せ、運動で肥満を解消することも大切です。ケースによっては、尿酸の生成を抑制する薬や、尿酸の排泄を促す薬などが処方されます。
メタボリックシンドロームにも注意

肥満、特に内臓まわりに脂肪が溜まってお腹がぽっこり出ている「内臓脂肪型肥満」の方は、血圧、血糖、脂質値などの異常を来たしやすく、その結果、高血圧、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)などの生活習慣病が重なりやすいことがわかっています。
内臓脂肪型肥満があり、加えて血圧・血糖・血中脂質のうちの2つ以上が基準値を超えている状態を「メタボリックシンドローム」(内臓脂肪症候群)と言います(下記参照)。
メタボリックシンドロームの患者様では、血圧、血糖、脂質などの値がそれほど異常でなくても、それらが重なることによって動脈硬化が一層進展しやすくなり、ひいては心筋梗塞や脳血管障害など、生命にもかかわる心血管事故が起こるリスクを高くします。
メタボリックシンドロームの診断基準
【必須項目】
| 内臓脂肪型肥満:ウエスト周囲径(立位・軽呼気時・臍レベルで測定) |
|---|
| 男性 | ≧85cm |
| 女性 | ≧90cm |
+
【選択項目】下記3項目のうち2項目以上に該当
- 高トリグリセライド血症:≧150mg/dL
かつ/または
低HDLコレステロール血症:<40mg/dL - 収縮期(最大)血圧:≧130mmHg
かつ/または
拡張期(最小)血圧:≧85mmHg - 空腹時高血糖:≧110mg/dL

